教員インタビュー
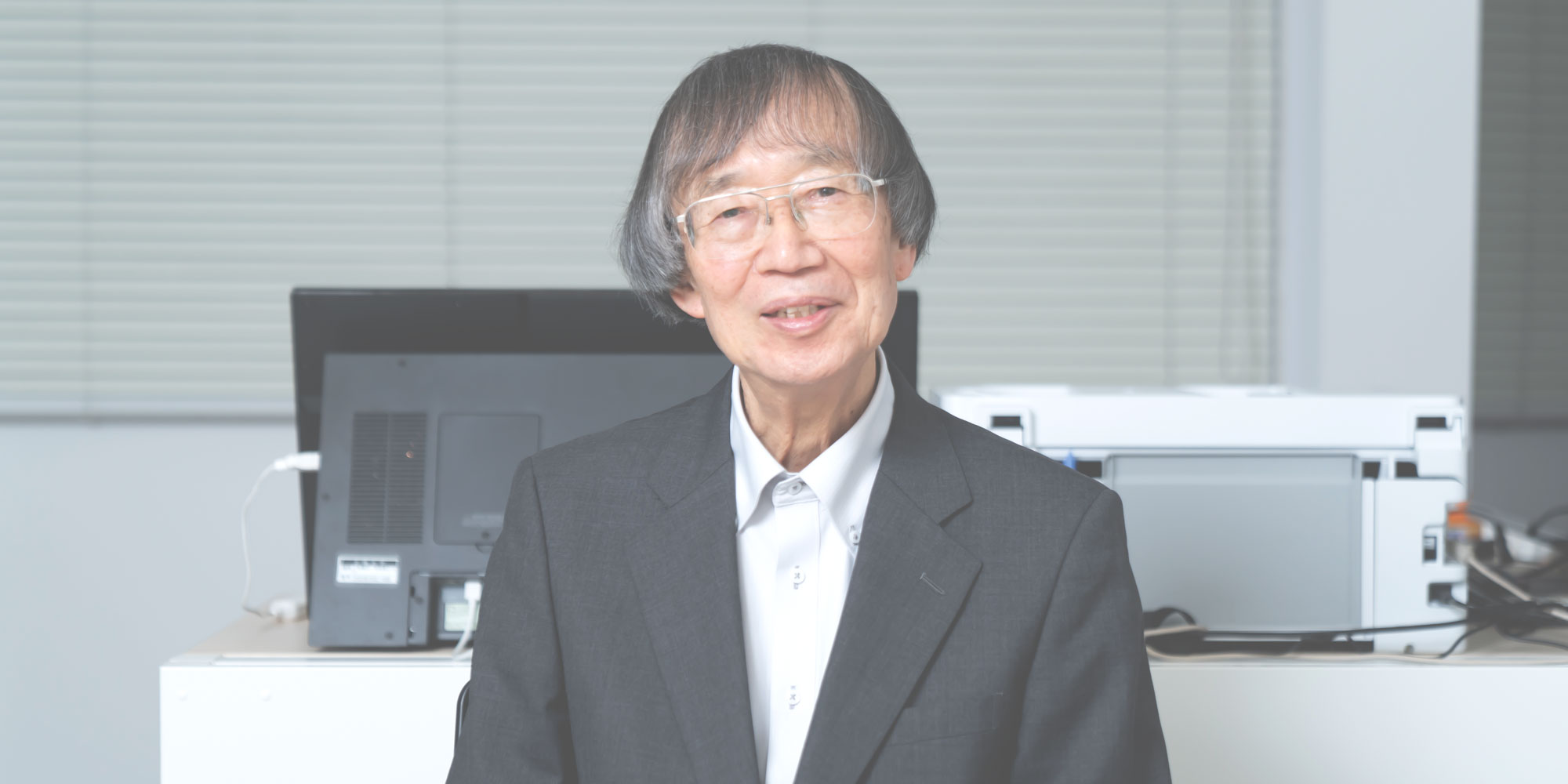
人間はいつでも
変わることができる
林 洋一
教授
専門分野/生涯発達心理学、パーソナリティと社会性の発達、
認知症心理検査、原子力災害と人間行動
発達という言葉からは、赤ちゃんが大人になるまでの心身の変化を思い浮かべる人が多いと思います。身体が大きくなるとか、それまでできなかったことができるようになるという前向きの変化です。それは間違いなく「発達」なのですが、実は、大人になってから年を重ねて死にいたるまでの時期にも、前向きの変化、つまり発達はあるのです。
たとえば、最近は高齢の方でもスマートフォンを普通に使っていますね。
これは、高齢者でも新たなことを学び、それを生活に活 かすことができることを意味します。たしかに加齢に伴う心身の変化は存在します。物忘れが多くなったり、人の名前が直ぐに思い出せなかったりするかもしれません。しかし、高齢者は物事を深く考えたり、人と人との関係を調整したり、利害の対立をうまく処理することもできるのです。
高齢者の中には、認知症になる人もいます。しかし、最近では、認知症の原因物質に直接作用する薬が開発されています。その薬の効果を判定する方法の一つとして、実は、心理検査が大きな役割を果たしているのです。かすことができることを意味します。たしかに加齢に伴う心身の変化は存在します。物忘れが多くなったり、人の名前が直ぐに思い出せなかったりするかもしれません。しかし、高齢者は物事を深く考えたり、人と人との関係を調整したり、利害の対立をうまく処理することもできるのです。
高齢者の中には、認知症になる人もいます。しかし、最近では、認知症の原因物質に直接作用する薬が開発されています。その薬の効果を判定する方法の一つとして、実は、心理検査が大きな役割を果たしているのです。

友だちって何だろう?
西浦 真喜子
講師
専門分野/社会心理学、同性友人の魅力
主な担当科目/社会心理学概論、心理学実験
大事な存在だろうということはわかっても、いざ定義しようと思うとなかなか難しいのが「友だち」という存在です。見方を少し変えて、「友だちに感じる魅力」という点で考えると、「一緒にいて安心できる」「良い刺激をくれる」ということが挙げられます。しかし、すべての友だちがそうとは限りませんし、同じ相手であってもいつも同じ魅力を感じられるわけでもありません。では、どうすればその魅力を感じられるようになるのでしょうか。私は、その問題を解決するヒントが「距離をとること」にあると考えています。社会心理学では調査や実験などの手法を用いて、その真理を明らかにしていきます。もちろん、うまくいくこともいかないこともあります。しかし、どのような結果であれ、「友だち」という存在を見直したり、より深く理解したりすることにつながります。さらには、他の人間関係に応用することもできるかもしれません。そのような可能性を生み出せる心理学の研究はとても興味深いです。私自身、そう思って学生のみなさんと学んでいます。
ること」にあると考えています。社会心理学では調査や実験などの手法を用いて、その真理を明らかにしていきます。もちろん、うまくいくこともいかないこともあります。しかし、どのような結果であれ、「友だち」という存在を見直したり、より深く理解したりすることにつながります。さらには、他の人間関係に応用することもできるかもしれません。そのような可能性を生み出せる心理学の研究はとても興味深いです。私自身、そう思って学生のみなさんと学んでいます。