 オフィシャルサイト
オフィシャルサイト
 オフィシャルサイト
オフィシャルサイト

清水 芳行 教授
- TEACHER’S KEYWORD -

Q.なぜ臨床工学技士の道に?
医療従事者の方にお世話になって、自分もそういう道に進みたいなと
僕は高校を卒業して、臨床工学技士の養成校に進みました。医療系を志したきっかけは、中2の時に腎臓を悪くして4か月ぐらい入院したことがあるんですよ。その時に、色んな医療従事者の方にお世話になって、自分もそういう道に進みたいなと思ったのがきっかけです。
最初は、放射線技師とか他の職業も考えていたんですが、ちょうど僕が高校を卒業する前の高2の時に、東海地区に初めて愛知県に臨床工学技士の養成校ができて、調べていくうちに面白そうだなと思って、その道に進みました。
Q.入ってから勉強はどうでした?
とにかく大変でした
想像以上に大変でした。大学に進学した友達と比べると、勉強や生活に対する時間の取り方とかのリズムが全然違っていました。とにかく、医学、医療の勉強が大変でしたね。
臨床工学技士は工学系の勉強もあるんですよ。電気工学とか電子工学とか機械工学とかがあって、高校で文系だった自分は、結構、苦労しました。
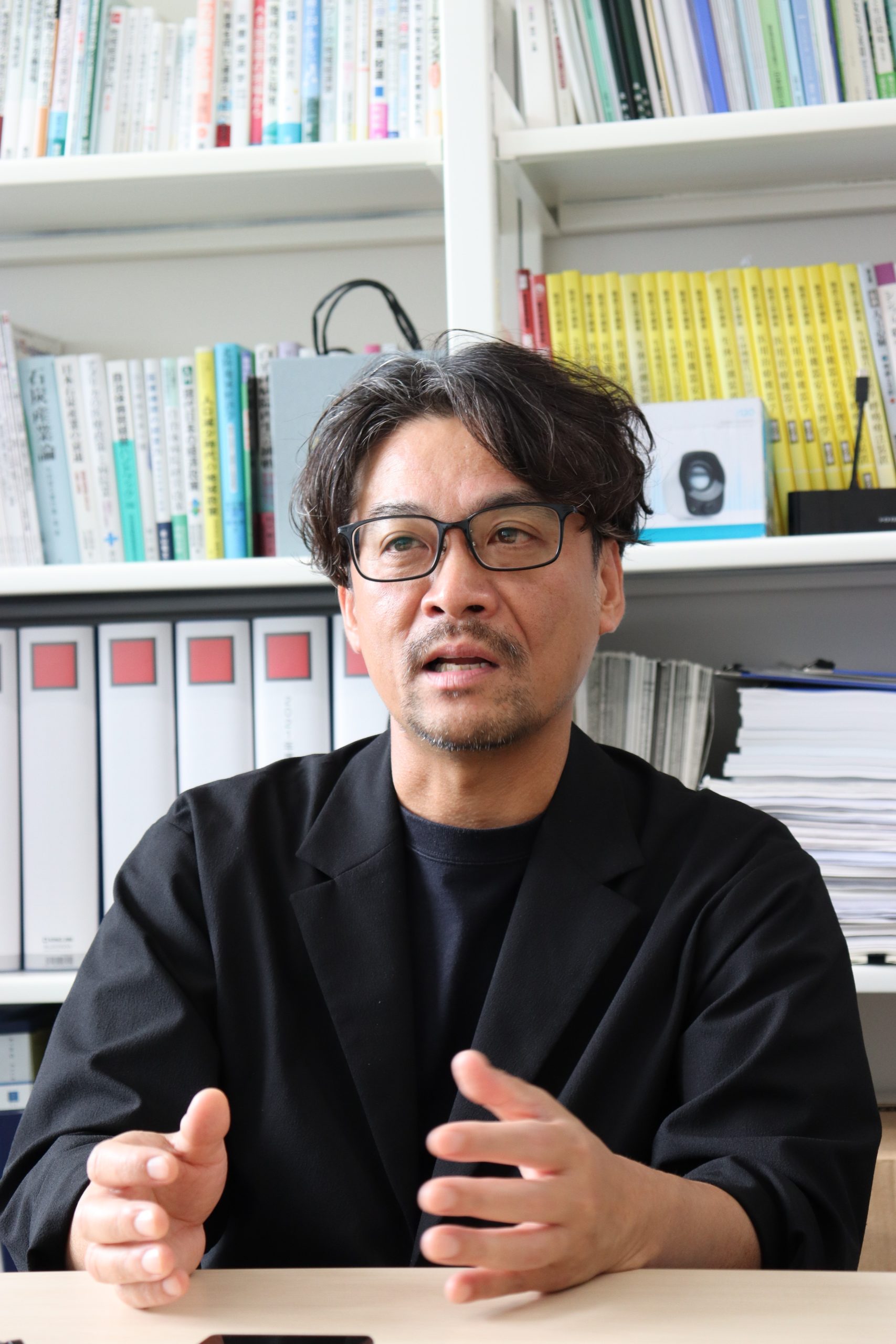
Q.臨床工学技士の資格を取得した後から大学院に進学されるまでに何をされていたんですか?
人が生死を彷徨う現場に
養成校を出て、1996年に臨床工学技士の国家試験合格を合格して、愛知県の三河地方にある安城更生病院で働き始めました。そこは高度急性期病院だったのですごく忙しかったですね。心臓の手術とか集中医療に携わっていたんですけども、本当に大変でした。医療人としての基礎がない中で、患者さんはガンガン来て緊急手術とかも沢山あって、人が生死を彷徨う現場をたくさん見ました。本当に大変でした。
Q.その後は?
先生になりたかった
3年ぐらい経った時に、僕が通っていた学校から「講師にならないか」って誘いがありました。もともと、高校生の時に先生になりたかったというのもあるんですよ。それで、「やってみようか」ということで母校に戻ったんです。その時、まだ26歳。すごく楽しかったですね。自分も若いし、学生も若いし、年齢が近いから、時には友達のように接しながらガンガンやっていました。熱血漢でやっていたから、学生もついてきてくれていたんですよね。ただ、そこは29歳の時に辞めました。

Q.なぜ、辞めたのですか?
中国の山東大学に留学へ
中国に留学したからです。学校が毎年中国に学生を連れて、人体解剖研修に行っていたんですよ。僕もそれに毎年ついて行っていました。そこで、すごく親しくなったドクターの夫婦がいるんですが、その人たちが留学という形で中国で学んでみないか?って誘ってくれたんです。それで、自分も海外に住んでみたいというか、そういった希望は若いうちは誰でもあると思うんですけど、学生の時にできなかったので、20代最後に行ってみようかと思って、中国の山東大学に留学しました。
語学を学びながら時々、病院見学とか行って、最終的に上海第二医科大学(現:上海交通大学)の医学部に行こうと思っていたんですね。ただ、結局、半年ぐらいで帰ってきました。中国の生活はすごく楽しかったし、充実していたんですけど、不安もあって。仮に医学部に行ったら、35、36歳になっているので年齢的に大丈夫かなって。当時、友達は皆キャリアを積んで、良いポジションについていたんですよね。そういったこともあって、結局、帰ってきました。
Q.帰国後はどうされたのですか?
学びたいという意欲が強く
資格はあるからどこでも勤めようと思えば勤められるんですが、やっぱり学びたいという意欲がすごく強かったので、地元の南山大学大学院に行きました。
Q.大学院の研究テーマは?
医療事故を社会学の視点から分析
当時、大きな医療事故が日本中ですごく起きていたんですね。例えば、都立広尾病院の点滴の取り違え事故や東京女子医大の人工心肺の事故とか、本当にすごく大きく報道された事故がたくさん起きていました。そこで、自分は医療機器の専門家だけど、医療の側から見るんじゃなくて、もっと社会学的に分析してみようという思いから、総合政策研究科で医療政策を学びました。指導教授は松戸武彦教授です。社会学の先生なので社会調査方法とか統計学とかを駆使して医療事故の原因分析をすべく、研究の道に進みました。

Q.今の研究テーマを教えてください。
医師の偏在と地域経済
大きく分けると2つありあます。1つ目は、医師偏在問題ですね。医師や技師とか医療従事者が都市部に偏ってしまって、過疎地域からどんどん去ってしまう。過疎地域から医療従事者が去れば、過疎地域の医療が成り立たなくなり、人口が減るんですよ。歳を取ると、病院がない所に住むかというと、そうじゃないですよね。都市部への人口の集中と過疎地域からの人口の流出がさらに進むわけで、それを博士課程の時にずっと研究をしていました。それは北海道を題材にしていたんだけど、北陸でも続けてやっています。まさに今、輪島とか奥能登とかは、地震が起きて医療が崩壊しかけている。人口が減っているから医療従事者も減っているのかについては議論の余地があるけど、病院が無くなれば、当然、人口も減るし、もっと過疎化が進む。じゃあ、能登の生活はこの先どうなるのかということを地域経済と関連付けて分析しています。
Q.2つ目の研究テーマについて教えてください。
医療従事者とスポーツ指導者のストレスを分析
2つ目は、医療のストレス問題。結構、ドクターとか看護師さんというのは、特に看護師さんとかは、病院を辞めてしまうんですね。資格を取ってせっかく働き始めても数年でその職業をやめてしまう。色んな原因があるんですけど、その一つにストレスがあるので、治療中の心拍データの周波数解析というのを進めています。例えば、どういったところでストレスがかかるのかが分かれば、交代したりとかちょっと休憩したりとかすることが出来ると思うので。やっぱりストレスがかかると、医療の安全にもよくないというデータがあるので、その分析を進めています。
あと、もう一つが同じような手法になるんですけども、スポーツハラスメント。スポーツ現場での暴力暴言です。これは、中高の時に部活でぶん殴られたりとか、「お前なんて帰れ」とか、そんな暴力とかでニュースになったりしていると思うんですけども、あれもやっぱり指導者のストレスですよね。どんなところで、「カッ」とするとか、どんなところで「ムカッ」とするのかっていうのを、やっぱり、心拍データから分析をしています。だから、地域経済という博士課程の時に研究していたものと、自分の専門分野の2つの分野にまたがって研究しています。

Q.先生が地域経済学に興味を持たれたのはいつですか?
北海道時代に地域格差を目の当たりにし
それは、北海道に行ってからです。北海道は本州と違っていて、札幌とそれ以外の地域で格差がめちゃめちゃあるんですよ。例えば、教育もそう。あと、もっとびっくりしたのは、交通網。電車とかバスがないとか、あるいは、どんどん減らされていたりしている。北海道に住んでいた時に大きな台風が来て、線路が流されたりとか壊れたりしたんです。そうすると、直すお金もないから、そのまま廃線になっちゃう。石川県ではそんなことってないですよね。何か起きてもすぐに直したりとかして、電車は維持するわけでしょ。医療も一緒で、病院が成り立たないと医者が来ないわけで。もしかしたら、そういった地域格差みたいなものは、自分の専門の医療でも起きているかもしれないということに興味を持ち始めたのが最初です。
Q.臨床工学技士でありながら、博士号は経済学。かなり変わった経歴ですね。
研究している人がいなかった
医師の偏在問題を調べていくうちに、これは医療側だけの問題じゃなくて、やっぱり地域経済との関連が強い。つまり、地域経済って何かって言うと、やっぱり、人口と労働市場ですね。地域に仕事があるかないか。地域経済は、地域で仕事が無くなったりすると、そこの産業が衰退する。そうなると、人口も減るし、人口が減ると医者も減るんですよ。これを明治時代から追っていたんですけど、地域ごとにはっきりしているんですよね。でもそれを、研究している人がいなかった。つまり、医療問題と地域経済を関連付けた研究が無かったんで、それをやってみたんですよ。
Q.大学HPの教員紹介の中で、「正解のないことに取り組むことへの重要性」に言及されていますが、これは自身の経験から感じたことですか?
正解は後になってからしか分からない。経験することが大事。
自分が生きてきて、色んな岐路があったわけですよ。病院を辞めて教員になる時もそうだし、留学もそう。帰って来てからも研究をしようとか、大学に行こうとか。あるいはもう一回病院に勤めようとか、辞めて大学教員になろうとか。その時に正解は分からないわけですよね。これ、後からなら分かるかもしれないけど、正解はない。今、北陸に来て学生たちと楽しく過ごして充実しているのも正解だよね。正解というのは後からしか分からないから、とにかく学生時代は色々と悩んだり、経験するのが大切。経験していない人生ほどつまらないものはないんじゃないのかなと思うんですよ。
僕は臨床工学技士の中では結構、変わった人だと思っているんです。普通は22歳で就職して、約30年間同じ病院で働いている友達たちもたくさんいる。対する僕は仕事を変えたり、研究したり、留学したりとか、変わった人生を送っている。でも、経験だけは誰にも負けていない。経験することは将来的に正解を考える上で大切なことなんじゃないって思っています。
*https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/teacher/y-shimizu2.html

MESSAGE
先生が北陸大学の学生に想うことや、
高校生へ伝えたい想いなどをお聞きしました。
INTERVIEWER COMMENT
実際にインタビューした学生が、
先生の新たな発見や魅力について記録します。
MATCHING INTERVIEW
同じキーワードを持つ先生や、
同じ学科の先生をご紹介。
INTERVIEWER COMMENT
常に学生の成長のことを考えている清水先生。メディアラボ生の中に清水先生のことを影で「イケオジ」と呼んでいる女子学生がいるのですが(笑)、インタビューをしてその理由がよく分かりました。とにかくまっすぐ。生き方がかっこいい。今後も学生に愛される先生でいてください。ありがとうございました!