 オフィシャルサイト
オフィシャルサイト
 オフィシャルサイト
オフィシャルサイト
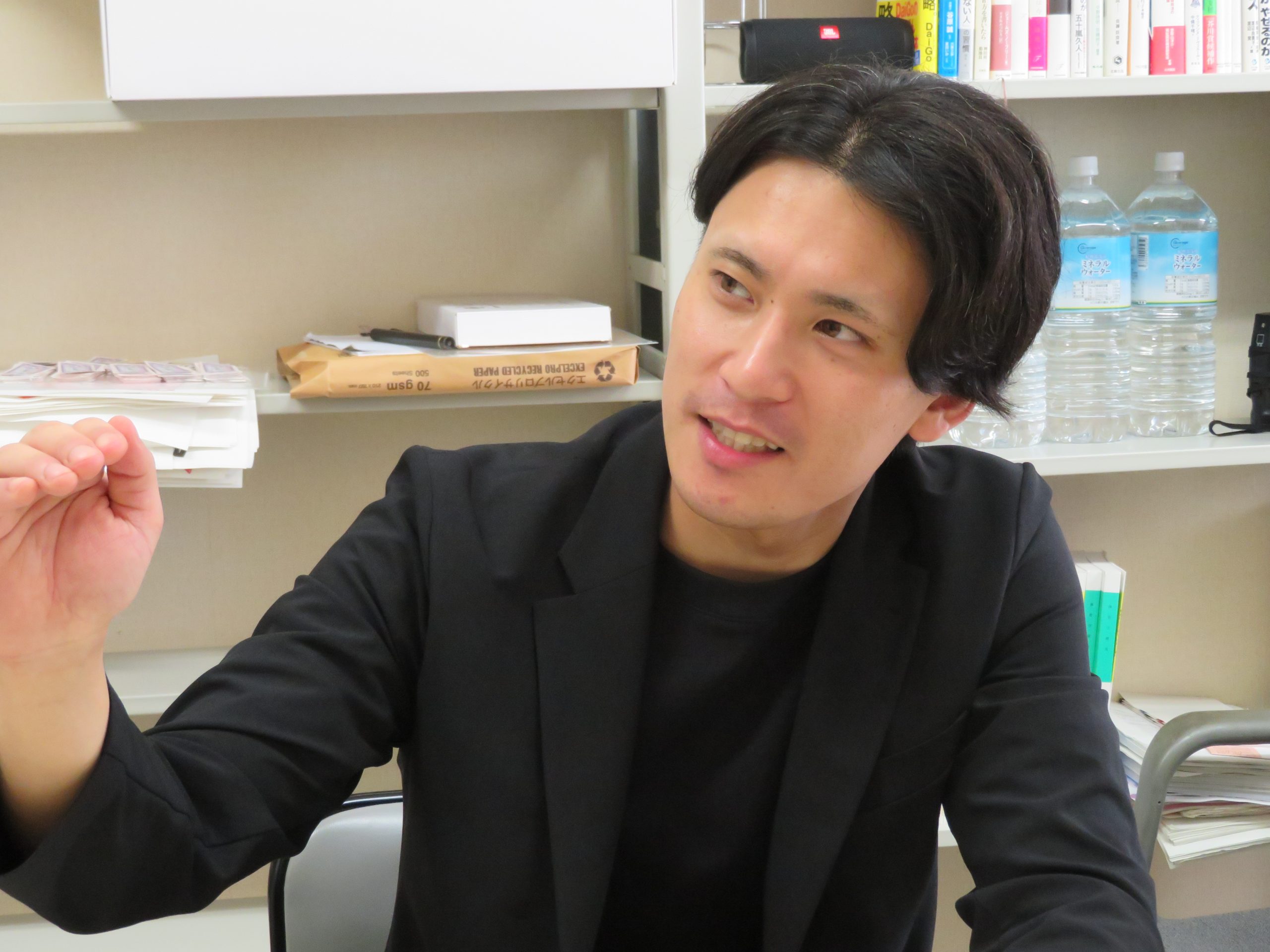
坂口 雄介 助教
- TEACHER’S KEYWORD -
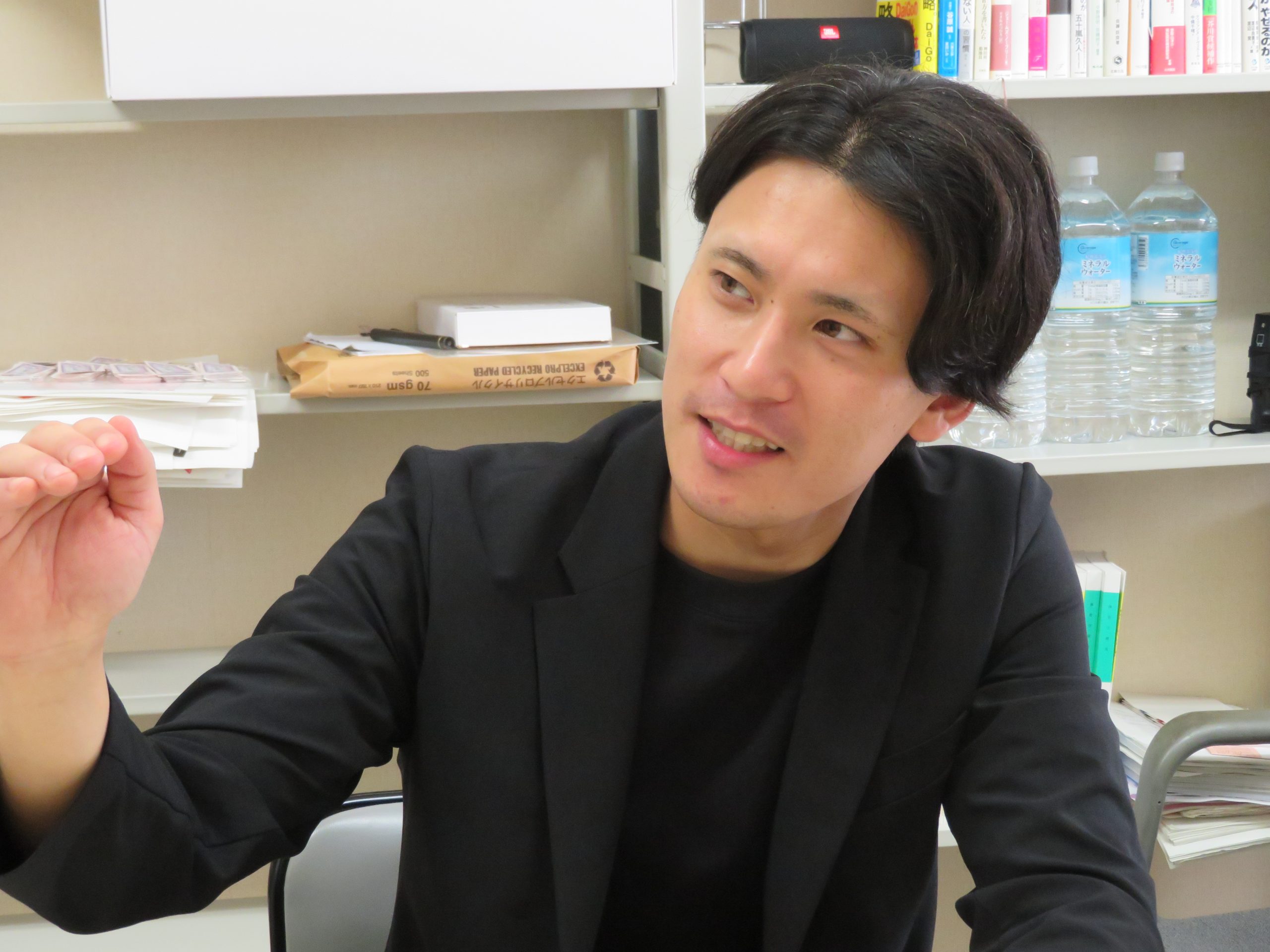
Q.出身大学を選んだ理由はなんですか?
大学でも剣道をやりたい
小学校の頃から、剣道をやっていました。その剣道を大学でもやりたいなと思っていて、地元の国立大にいきたいと思って金沢大学を受けたけど落ちちゃって(笑)勉強が得意ではなかったので、実技試験だけで入れる大学はないかなという正直かなり浅はかな思いで新潟大学を選びました。新潟大学に高校の先輩がいたことも大きかったですね。
Q.大学生活の4年間はどのような感じでしたか?
初めての学会が転機に
大学では1年から3年前期までと、それ以降とでまったく違う学生生活を送りました。1年から3年前期までは、ずっと部活をやっていましたね。授業にも出ないときもありましたし、出たとしても決して褒められた態度ではなかったと思います。そんな感じの生活が続いたのですが、3年生の夏に初めて学会に行ったことが大きな転機となりました。「研究って面白いなぁ」と感じて、3年生の後期からは、逆に部活をまったくしないで、先生の研究室に行ったり、院生の部屋にお邪魔したりしながら研究にのめり込んでいきました。

Q.その3年生の夏の学会は、どんな学会だったのですか?
スポーツ科学が専門だったので、その分野で一番大きい日本体育・スポーツ・健康学会が大阪であって、それに参加しました。
Q.大学院に進学しようと思ったきっかけはなんですか?
人の役に立ちたい
研究が楽しいと感じたからですかね。地域に出て現場の人と関わり、そこから見つかる課題とか疑問だとかを、ちょっとかっこよく言うと「学術的」に解決していく。「人間はどうして高齢者になるとつまずきやすくなるのか?」、「どうして交通事故に遭うのか?」というのを人間の側面から解析していく。現場に出ていろんな人と話す中で、この人の役に立てたらいいなぁという思いが進学を後押ししました。
Q.研究テーマとの出会いはなんですか?
初めての学会発表で研究が面白く
大学3年生の時に「学会に出てみたい」と先生に相談したら、「警察とのプロジェクトがあるよ。データもあるから、それを分析してみて」って。それが出会いですね。それで、交通事故を減らすために人間の認知機能や足の筋力のデータ分析をして、初めて学会で発表しました。3年生の2月のことで、そこから、あれよあれよという感じで、研究が面白くなっていきました。交通事故を減らすことと地域課題を解決することを、ずっと研究していました。

Q.研究テーマを高校生にも分かりやすく教えてください!
子どもたちの勉強のハードルを下げたい
研究テーマは、主に交通と教育と防災に関する運動機能解析と地域デザインです。例えば、交通の話では、今、ニュースでも話題になっている「どうして高齢者は車の運転中にアクセルとブレーキを踏み間違えてしまうのか?」というテーマがあります。踏み間違えた後に、「あっ、間違えている」って、なんで気づかないのか。これは認知機能の話ですね。思ったよりも動けないということを認識して、体力をつけて危ないって時に回避行動が取れるのか、そんなあたりを研究しています。
教育では、今の子どもたちの教育レベルは国際的に上位ですが、読解力などは低下しています。特に学ぶ意欲や学習の習慣が十分でないことが危惧されている中で、じゃあ子ども達が、いかに小さい頃から勉強というもののハードルを下げて、楽しく学べるか。そんな仕組みづくりに取り組んでいます。また、小さい頃の経験や出来事がその後のキャリアにどう影響を及ぼしているのかということにも興味があります。
防災では、石川県でいうと自然災害からの復興です。その中で、キーワードは、やっぱり「人間」。人との繋がりとかコミュニティの関係とか、そういうところを色々やっています。
Q.今後、他の分野で研究してみたいことはありますか?
経済分野とコラボしたい
今、経済経営学部という新しい分野の所属になりました。今後は「地域マネジメント」、「町づくり」、「地域活性化」という視点で色々な話をしていきたいですね。あと、学生の興味に合わせて、地域マネジメントと経済分野のコラボができたらいいなと思っています。

Q.大学の教員紹介のページ(*)をみると、「SDGsの達成とwell-beingの実現に向けた地域づくり」に関する研究をされています。その中で、改めてSDGsの意義を教えてください。
人々の「幸せ」を実現していく手段として「SDGs」がある
SDGsの17の目標の達成に向け、現在、日本をはじめ、世界各国で課題解決に取り組んでいます。しかし、本当に大切なのはその先で、SDGsに取り組むことは、あくまで手段であると思っています。もちろん、戦争を無くすことや物価高や飢餓、貧困を無くすことは大切だけど、「その先ってなんだろう?」と考えた時に、キーワードが「well-being」や「幸せ」、「幸福」になってくると思います。人々は「幸せ」を実現していく必要があり、その為の手段として、SDGsというものがあると思っています。
例えば、戦争が無くなった時に、その先の人々の生活や暮らしをどう考えればいいのか?戦争を無くすことをゴールにしていないだろうか?そんなことを常日頃、ニュースや色んな記事とかを見ながら考えています。
*https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/teacher/y-sakaguchi.html
Q.新潟県で大学生活を送られてきた中で、また、石川県に戻ってこようと思ったきっかけはなんですか?
生まれ育ったところに恩返しをしていく
これはやっぱり、自分の生まれ育った地域に恩返しをしたい。これに尽きます。自分が育ててもらった地域で、一緒に課題解決に取り組んでいきたいという思いがずっとあったので、10年ぶりに帰って来られてすごく嬉しい。夢がかなったという思いです。

MESSAGE
先生が北陸大学の学生に想うことや、
高校生へ伝えたい想いなどをお聞きしました。
INTERVIEWER COMMENT
実際にインタビューした学生が、
先生の新たな発見や魅力について記録します。
MATCHING INTERVIEW
同じキーワードを持つ先生や、
同じ学科の先生をご紹介。
INTERVIEWER COMMENT
インタビューを通じて、何気ないことが人生の分岐点になるんだなということを実感しました。私も自分の可能性を広げられるように、日々の生活を見直すことから始めてみようと思います。また、SDGsは手段にすぎず、その先にある幸せの実現が重要という考え方にはハッとさせられました。ありがとうございました!